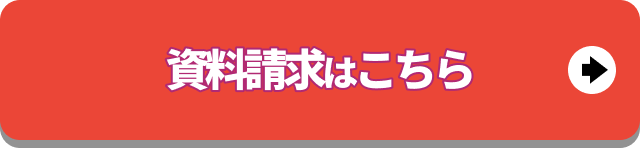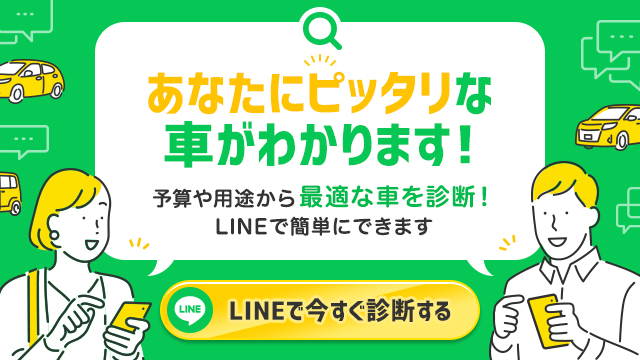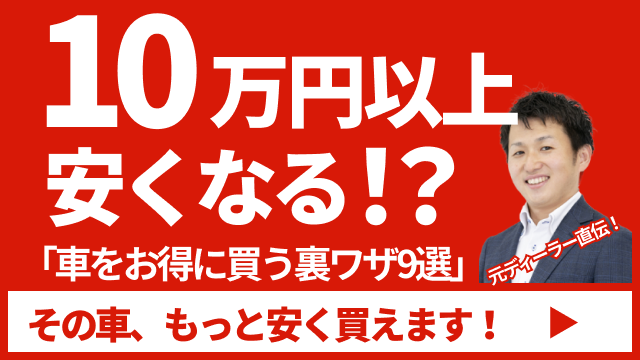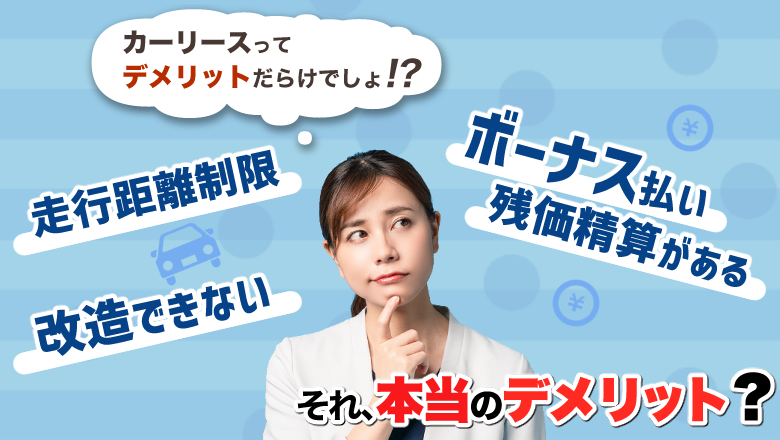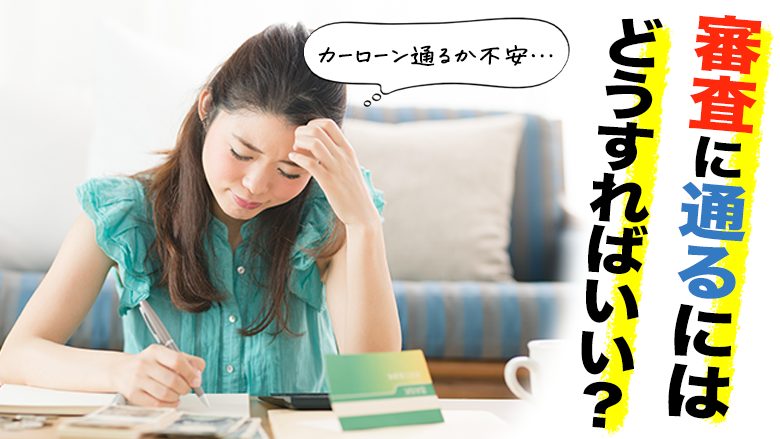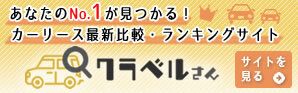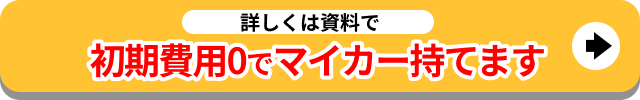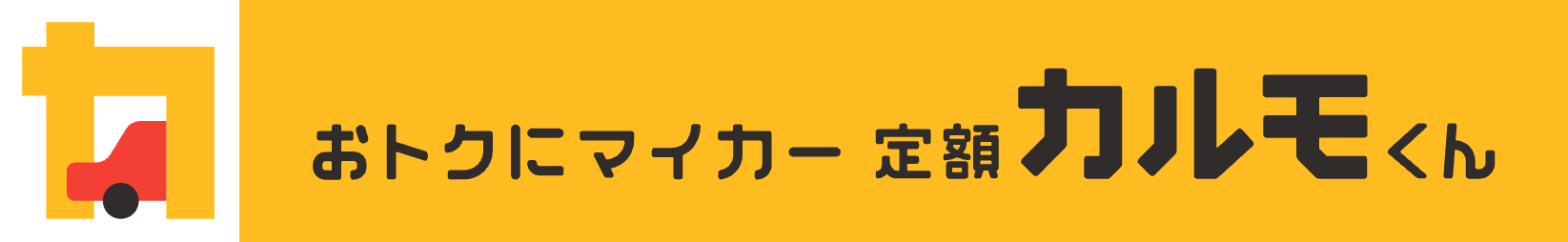バッテリーは車を動かすために必要な部品で、定期的な交換が欠かせません。バッテリーが正常に動かなくなると走行不能になるので、寿命やその前兆を正しく把握し、不具合を起こす前に交換などの処置を取ることが大切です。
ここでは、バッテリー交換のタイミングや寿命を知る方法、またバッテリー上がり時の対応、バッテリーを長持ちさせるポイントなどについて、自動車整備士・若林由晃さんの解説を交えて解説します。
- バッテリーの交換時期は車や使い方によるが、ガソリン車なら2~5年
- アイドリングストップ搭載車は、バッテリーの寿命が短くなる
- 電気系統のトラブルが起きたらバッテリーが劣化しているサインかも
車のバッテリーの寿命は?交換時期と目安について
バッテリーの寿命は一般的に2~3年程度といわれていますが、パワーユニットや車の使い方、環境などによって左右されます。
ガソリン車の場合は2~5年程度が交換時期の目安になるでしょう。アイドリングストップシステムを搭載している車は少し短く2~3年程度、ハイブリッド車は4~5年程度です。

とはいえ、ギリギリまで使用するとトラブルにつながりやすいので、後ほど解説するような方法でしっかり見極めて、適切なタイミングで交換しましょう。
〈バッテリーの寿命の目安〉
| 車のタイプ | 交換目安時期 |
|---|---|
| 一般的なガソリン車 | 2〜5年 |
| アイドリングストップ搭載車 | 2~3年 |
| ハイブリッド車 | 4~5年 |
●一般的なガソリン車のバッテリーの寿命は2~5年
バッテリーのメーカー保証は、使用期間2~3年、走行4万~10万kmなどとなっていますが、実際は保証期間を過ぎても使えるケースが多くあります。長く使えるだけに、バッテリーの状態から交換時期を見極めることが重要です。
●アイドリングストップ搭載車のバッテリー寿命は2~3年
エンジン停止と再始動が繰り返されバッテリーに負荷がかかりやすいことから、寿命は2~3年と一般的な車よりも短い傾向があります。メーカーの保証期間も1年半ほどと非常に短くなっています。
●ハイブリッド車のバッテリー寿命は4~5年
ハイブリッド車は、電気モーターを動かすための駆動用バッテリーと、ハイブリッドシステムの始動やエアコン、オーディオなどの電装品を使用するための補機バッテリーの2種類のバッテリーを搭載しています。
ここでいうバッテリー寿命は、補機バッテリーを指します。補機バッテリーはガソリン車のバッテリーとほぼ同じ仕組みであり、定期的な交換が必要です。寿命は4~5年と、ガソリン車とほぼ同じか、若干長い程度といえるでしょう。
ハイブリッドのメインバッテリーである駆動用バッテリーは大型であり、一般的にリアシート下や荷室下部、またはセンターコンソール下などに格納されています。駆動用バッテリーの寿命は補機バッテリーよりも長く、ほとんどのハイブリッド車においてメーカー保証が5年、走行距離10万kmに設定されていますが、実際は10年以上使用できるケースも多く、車の寿命まで交換が必要ないケースも少なくありません。
もしかしてバッテリーの寿命?と思ったときの確認方法

そろそろバッテリーの寿命かな、と気になったら、以下の点をチェックしてみましょう。
外観や液量など、目視で確認する
バッテリーの寿命が近付くと、外観に変化が現れるケースもあります。一般的にバッテリーの寿命といわれる時期が近付いてきた場合や、エンジンがかかりにくいなどの不具合がある場合はバッテリーを目視チェックしてみましょう。
本体が膨らんでいる、端子部分が粉をふいたようになっている場合は寿命が近付いています。また、バッテリー液が漏れている場合も交換が必要です。
漏れが確認できなくてもバッテリー液が下限である「LOWER LEVEL」を下回り、補充してもすぐ減るようであれば異常があります。また、本来は透明であるバッテリー液が茶色く変色している場合も寿命は近いといえるでしょう。
電圧や比重をチェックしてみる

バッテリーの電圧や比重を調べてみるのも、バッテリーの寿命判断に有効な手段です。バッテリーの電圧は、12.5Vを下回るようであれば、バッテリーが劣化しているサインといえます。
また、バッテリーが十分充電されているのに比重が正常値である1.28前後に戻らない場合は要注意です。
電圧や比重の計測は、専用の器具を使用します。普段から車のメンテナンスなどを自分でしない方には若干ハードルが高い作業になるので、給油の際などにプロにチェックしてもらうことをおすすめします。

現在はメンテナンスフリータイプのバッテリーも普及しています。メンテナンスフリータイプはインジケーターで液不足や充電不足などが確認できるようになっているので、定期的にチェックしましょう。
バッテリーの寿命が近い?交換時期を知らせる3つの前兆
バッテリーの寿命が近付くと、以下のような症状が現れます。普段運転しているときに「あれ?」と違和感を抱くことがあったら、バッテリーの劣化を疑ってみましょう。
エンジンがかかりにくい

車のエンジンは、バッテリーから流れた電流がセルモーターを回転させて始動します。このとき、多くの電力を消費するので、バッテリーが劣化するとセルモーターの回転が弱まり、エンジンがかかりにくい、エンジンをかけるときの音が弱いといった症状が出てきます。
アイドリングストップ機能が使用できない

バッテリーが劣化すると、アイドリングストップに必要な電力が不足して機能が使えなくなることがあります。アイドリングストップ機能がONになっているにもかかわらず、信号待ちや渋滞時にエンジンが止まらない場合は、バッテリーを確認しましょう。
パワーウィンドウの動作が遅い
パワーウィンドウの開閉にもバッテリーからの電気を消費します。当初と比べて開閉に時間がかかるようになった場合、バッテリーの寿命が近い兆候かもしれません。
ヘッドライトはバッテリーの寿命の判断基準になりにくい

現在はバッテリーの性能が上がり寿命寸前まで通常どおりに作動することが多いので、上記のような前兆がほぼないケースも少なくありません。
また、かつてはヘッドライトが暗くなることが寿命のサインのひとつであるとされてきましたが、昨今ではヘッドライトの明るさはバッテリーの寿命の判断基準にはなりにくいといえます。
ヘッドライトはこれまでハロゲンがおもに使用されていましたが、今は少ない電力で明るい光を発するLEDが主流になっているからです。
バッテリー上がりのときはどうする?

バッテリーに蓄えられていた電気が少なくなって、エンジンがかからないなど車が適切な動作をしなくなった状態を「バッテリーが上がる」といいます。バッテリー上がりはなぜ起きるのか、どう対処しらたいいのか、解説します。
バッテリーが上がる原因とは
電気が使われるだけの状態、例えば以下のような状況になるとバッテリーが上がることがあります。
- ヘッドライトやルームライト、ハザードランプなどを長時間つけっぱなしにした
- 長時間半ドアのままにした
- エンジンが停止しているあいだに長時間エアコンを使った
- 長期間車を動かさなかった(自然放電によるバッテリー上がり)
- バッテリーが寿命を迎えた
バッテリー上がりの対処法
バッテリーが上がってしまった場合は、以下の3つのいずれかの手段をとることになります。
ブースターケーブルを使用してほかの車に電気を分けてもらいジャンピングスタートをする

ほかの車(救援車)から電気を分けてもらい、バッテリーを充電する方法です。
●ジャンピングスタートの手順
救援車のバッテリーと故障車のバッテリーを、ブースターケーブルを使用して接続します。ケーブルをつなぐ場所に加え、つなぐ順番も非常に重要なので、説明書をよく読んで間違いのないように接続しましょう。正しく接続できたら救援車のエンジンを入れ、しばらくそのままにして充電します。
5分程度経ったら、救援車のアクセルを踏み込み回転数が高い状態を保ちます。その後、故障車のエンジンを始動し、かかれば成功です。
ブースターケーブルは、つないだときと逆の順番で取り外してください。
●ジャンピングスタート時の注意点
救援車は、同じ電圧の車を使用しましょう。自家用乗用車の場合は通常12Vですが、大型トラックなどは電圧が異なります。また、ハイブリッド車はほかの車の救援はできませんが、ハイブリッド車の補機バッテリー上がりの場合はガソリン車の救援を受けることが可能です。
ジャンプスターターを活用する

ジャンプスターターという、車のバッテリーの充電ができるモバイルバッテリーを使用してバッテリーを充電する方法もあります。原理は救援車を使用してのジャンピングスタートと同じですが、救援車がなくてもバッテリーが充電できます。
ロードサービスを手配する
ブースターケーブルやジャンプスターターがないなど、ジャンピングスタートが難しい場合は、ロードサービスを手配しましょう。任意保険に加入している場合はロードサービスが含まれていることがあるので、保険会社に確認することをおすすめします。

ジャンピングスタートは、あくまでも応急処置です。バッテリーが復活したとしても一時的なものである可能性が高いので、できるだけ早く整備工場やディーラーなどで点検してもらうことをおすすめします。
バッテリー上がりを放置するとどうなる?

バッテリーが上がった状態のまま車を放置すると、重大なトラブルを引き起こす可能性があります。その例を挙げてみましょう。
コンピューターが初期化される
今の車は、ほとんどの機能を車載ECU(Electronic Control Unit)で制御しています。
バッテリーが上がるとECUに電力が供給されなくなり、設定がすべて初期化されるおそれがあります。ECUが初期化すると、再始動しても元のようには車が動かない可能性が高く、再学習が必要になることも。場合によっては、ディーラーなどでの調整が必要なケースもあります。
バッテリーの寿命を迎えるケースも
まだ新しく、本来であれば十分寿命が残っているバッテリーでも充電ゼロの状態で長時間放置するとバッテリー内部の部品の劣化が進み、バッテリーの寿命を大幅に縮めてしまう可能性があります。
バッテリー上がりは自然回復することはないため、放置すればするほどバッテリーは傷むと考えましょう。
車を動かさないことによる弊害が出てくる
車は、長期間動かさないでいると劣化します。特にエンジンはオイルが落ちてしまい、エンジンオイルが摩擦をやわらげるクッションの役割を果たせない状態になっています。この状態でエンジンを始動させるとシリンダーとピストンが摩擦を起こし、エンジンにダメージを与えるのです。
またタイヤも同じ場所に重さがかかり続けるので、変形し元に戻らなくなります。さらに燃料タンクにガソリンが残っていると、ガソリンが劣化して腐り、再始動時に大きなトラブルを引き起こすことになりかねません。

バッテリーが上がったまま放置しても、いいことはひとつもありません。まだ新しい車であっても、バッテリーが上がった状態のまま年単位で放置すると、廃車になる可能性もゼロではないのです。できるだけ早くプロに依頼して点検、交換をしましょう。
バッテリー交換にかかる費用

バッテリー交換の工賃そのものはそれほど高額ではなく、1,000~3,500円程度です。ガソリン車よりも電気自動車やハイブリッド車のほうが高い傾向があります。
バッテリー本体の価格は車種や種類によってさまざまですが、安いものであれば5,000円程度、高額なものの中には40,000~50,000円程度するものもあります。メーカー純正品のバッテリーであれば20,000円前後が目安になるでしょう。
また、バッテリーの交換時には古いバッテリーの廃棄料も必要です。サービスとして無料で引き取ってくれる業者もありますが、500円~3,000円程度の廃棄料がかかるのが一般的です。
バッテリーの寿命を縮めるNGな乗り方

次に挙げるようなケースはバッテリーの消耗を早めている可能性が高いです。できるところから改善して、交換時期を先に延ばせるよう工夫してみましょう。
車に乗る頻度が少ない、短距離走行が多い
車のバッテリーは、走行してエンジンを回転させることで充電されます。そのため、車に乗る頻度が少ない場合や短い距離しか運転しない場合はバッテリーが充電不足になりやすく、消耗を早めてしまいます。
また、充電が溜まっていない状態でエンジンスタートとストップを繰り返すと、充電がなくなってバッテリーが上がる可能性があります。
【改善方法】
定期的に長い距離を走行すると、バッテリーの消耗を防げます。十分に充電するには、1週間に1回30分程度の走行が必要です。
夜間に乗ることが多い
夜間走行では、日中の走行よりも多くのライトを使用します。ライトを使用する時間が長いと、電気の使用量が蓄電量を上回る過放電になりやすく、バッテリーの劣化が早まります。
【改善方法】
夜間の使用回数が減らせない場合は、電力消費量が比較的少ないLEDなどの電球に変えるだけでもバッテリーの負担を減らせます。
ライトやスイッチなどを常時使っている
ライトや電装品のスイッチが長時間ついたままの状態は、バッテリーに負担がかがります。ライトやエアコンなど車内機器をオンにしたままエンジンをかけるのも、エンジンと車内機器の両方に電気を送る必要が生じて、バッテリーが消耗しやすくなります。
【改善方法】
エンジンが止まった状態で車内機器を使用するのは、できるだけ避けましょう。ライト類は安全のために必要なものは気にせず使用するべきですが、室内の演出のためのイルミネーションなどはバッテリーの負荷が気になる場合はOFFにすることをおすすめします。
電気を多く消費するアクセサリーを使用している
カーナビやドライブレコーダー、イモビライザーなど、電気の消費量が多いアクセサリーを搭載していると、バッテリーの消耗が早まります。スマートフォンやタブレットを頻繁に車で充電している場合や、カーオーディオに凝っている場合も要注意です。
【改善方法】
使用するアクセサリーを減らしたり、電力消費の少ないものに変えたりして、バッテリーの負担を減らしましょう。
きびしい気温下で車に乗る
バッテリーは寒さや暑さに弱く、20〜25度程度の環境でないと本来の性能が発揮されません。とりわけ寒さに弱く、外気温が0度で約20%、マイナス20度では約50%性能が低下するといわれています。また、エアコンも多くの電気を消費するため、よりバッテリーへの負担が大きくなります。
【改善方法】
寒い地域の場合は、寒冷地仕様のバッテリーを使用することで、寒さによる性能ダウンやバッテリー上がりを防止することができます。また、夏場は直射日光を避けられる屋根付きの駐車場に車を停めたり、冬場はカバーをしたりして、外気の影響を極力少なくする工夫も大切です。

今はドライブレコーダーやコネクティッド機能が使用できる大型ディスプレイなどを備えた車も多くなっています。さらに車内でスマートフォンなどを充電する頻度も高いのであれば、大容量のバッテリーへの載せ替えを検討してみてもいいかもしれません。
バッテリーを長持ちさせる方法

バッテリーを長持ちさせるには、日ごろのメンテナンスも重要です。バッテリーの劣化を防ぐためにしておきたいおもなポイントは、以下の2つです。
1. 定期的に点検と補水を行う
バッテリーに充填されている硫酸は少しずつ減っていきます。液がない状態が続くと、最悪の場合は火災が発生してしまうおそれもあるため、1~6ヵ月に1度のペースでバッテリーの点検と液の残量確認を行いましょう。
バッテリー液は、容器に記載されている「LOWER LEVEL」と「UPPER LEVEL」のあいだが適量です。「LOWER LEVEL」に近い場合はバッテリー液を補充しましょう。
2. バッテリー上がりを起こさない
バッテリーが1回でも上がってしまうと、本来の性能まで回復しなくなるだけでなく、新品との交換が必要になる場合もあります。バッテリー上がりを起こさないためにも、車内機器の使いすぎやライトの消し忘れ、室内灯が点灯したままになる半ドアなどにも十分注意しましょう。

バッテリー上がりを起こしたら、交換が基本と考えてください。普通に使用できたとしても、またすぐにバッテリー上がりが起きる可能性が高く、無理に使い続けてもメリットはありません。
「クルマって面倒…」ですよね。
もっとラクな車の持ち方あります
車を持つと、日頃のメンテ、車検、税金といろいろたいへんですよね。「いつ何をするべき?」「どこに頼む?」「いくら必要?」と考えなくちゃいけないことだらけです。
ですが、もっと気楽にマイカー生活を送る方法があります。今、利用者急増中の話題のサービス「カーリース」です。
車を持つときの費用も、メンテナンスにかかる費用もまるっとまとめて月々定額払いにできるカーリースなら、いろいろなことがラクになります。
中でも、業界最安水準の料金*で、申込者数20万人を突破した「おトクにマイカー 定額カルモくん」がおすすめです。
*文末の制作日における調査結果に基づく。調査概要はコンテンツポリシー参照

「定額カルモくん」について詳しくはこちら↓をご覧ください。
サービスガイド(パンフレット)もございます
買うのと何が違うの?なぜそんなに人気なの?といった疑問にお答えする内容となっています。ぜひご覧ください(郵送もダウンロードも可能です)。

バッテリーの寿命についてのよくある質問

バッテリーの寿命や交換時期についてよくある質問をまとめました。
バッテリーの寿命が近くなるとどんな症状が出る?
エンジンがかかりにくくなったり、アイドリングストップ機能をONにしていても作動しなかったりすることがあります。また、バッテリーが膨らんでいる、電流や比重が正常値とは異なる値を示す場合も寿命が近付いているサインといえます。
車のバッテリー寿命は10年程度って本当?
種類や車の乗り方などによっても変わってきますが、ガソリン車で2~5年、アイドリングストップ車は2~3年でガソリン車よりも若干短い傾向があります。ハイブリッド車は4~5年程度が一般的な寿命です。
バッテリー上がりを起こしたら交換するべき?
バッテリー上がりは、バッテリーに大きなダメージを与えます。充電すればとりあえず使えるケースもありますが、一度劣化したバッテリーは回復することはありません。またすぐにバッテリー上がりを起こす可能性が高いため、交換するのが望ましいでしょう。
バッテリーの寿命は延ばせるの?
バッテリーが十分充電できるように定期的にロングドライブをしたり、保管場所に気を付けてあまり低温にならないようにしたりなどの対策を心掛けましょう。また、電装品の使用を控えめにするなど、バッテリー上がりを起こさないようにすることも劣化を遅らせ、結果的に寿命を延ばすことにつながります。
車のバッテリーは自然回復する?
車のバッテリーは、自然回復することはありません。そのため、バッテリーが上がってそのまま放置しても直ることはないので、プロのチェック、整備を受けましょう。
※この記事は2024年1月5日時点の情報で制作しています